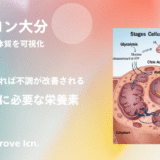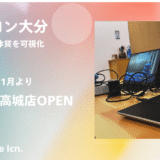前回のブログでは、糖代謝の仕組みやエネルギー生成の基本について解説しました。
今回は、その糖代謝の過程において欠かせない “マグネシウム” に焦点を当てたいと思います。
マグネシウムは「ミラクルミネラル」とも呼ばれ、代謝や神経、筋肉など、人体のさまざまな機能を支えている栄養素です。
この記事では、マグネシウムの役割や不足による影響、摂取のポイントについてわかりやすくまとめてみました。
\\今の不調と体質を可視化//
マグネシウムと糖代謝の関係

マグネシウムは、糖をエネルギーに変える「代謝」に深く関わっています。たとえば、ATP(アデノシン三リン酸)という細胞のエネルギー通貨を活性化するには、「ATPase」という酵素が必要です。この酵素が働くためには、マグネシウムが不可欠です。
つまり、「マグネシウムなしではエネルギーが作れない」と言っても過言ではありません!
そのため、マグネシウムは糖代謝の根幹を支える重要なミネラルです。
ミトコンドリアとマグネシウム

細胞の中にあるエネルギー工場「ミトコンドリア」も、マグネシウムがなければ正常に機能しません。
ビタミンB群(特にB1やB2など)を「使える形」に変えるためにも、マグネシウムは必須です。また、ビタミンDの活性化にも深く関わっています。
体内には約25gのマグネシウムが存在しており、その約60%が骨、残りは筋肉や神経などに存在します。また体内の99%は細胞内にあり、血液(細胞外液)中にはわずか1%未満。つまり血液検査ではマグネシウムの不足を正確に把握しづらいという難しさがあります。
マグネシウムが不足するとどうなるか?

ノーベル賞受賞科学者 ライナス・ポーリング博士も「すべての病気の根源はミネラル不足にある」と述べたように、マグネシウムの欠乏は多くの不調を招く可能性があります。
※マグネシウム不足が引き起こす主な症状:
・不安やパニック発作:マグネシウムは副腎(抗ストレスホルモン)をサポートします。
・うつ症状:神経伝達物質「セロトニン」の生成にマグネシウムが必要です。
・不眠:睡眠ホルモン「メラトニン」の生成にマグネシウムが必要です。
・糖尿病:マグネシウム不足は筋肉細胞のブドウ糖を取り込みを担う「GLUT4」の発現を妨げ、耐糖能を低下させます。
・高血圧・筋肉のけいれん(こむらがえり):カルシウムの細胞内蓄積を防ぐブレーキ役として、マグネシウムが働いています。
マグネシウムの過剰は心配ない

サプリメントや食品でのマグネシウム補給について、過剰症の心配は比較的少ないとされています。
多くの場合、摂りすぎたマグネシウムは腸で吸収されず、下痢として排出されます。ただし、敏感な方はごく少量(例:にがり1滴)でも腸に影響が出ることがあるので、体調に合わせて少しずつ試すのが安心です。
\\今の不調と体質を可視化//
マグネシウムを効果的に摂るには

栄養療法の観点では、不調を改善するために1日に400〜500mg程度のマグネシウムが推奨されることがあります。しかし、これを食品だけで満たすのはなかなか大変です。
食事からの摂取が理想ですが、不足気味の方やすでに体調に変化を感じている方は、サプリメントの併用も選択肢のひとつです。
※サプリメントの注意点!
・一度に大量に摂取すると、浸透圧の影響で下痢を引き起こすことがあります。
・少量(一回50mg程度)から様子を見ましょう。
・マグネシウムの吸収率は30%程度とされ、腸内環境や胃酸の状態が吸収の効率に影響します。
吸収を阻害する要因
マグネシウムの吸収を妨げる要素には、以下のようなものがあります!
1、加工食品に含まれるリン酸塩(鉄やカルシウムの吸収も妨げます)
2,高脂肪食や果糖の過剰摂取(吸収を阻害する可能性)
3,飽和脂肪酸との結合による影響
マグネシウムを多く含む食材
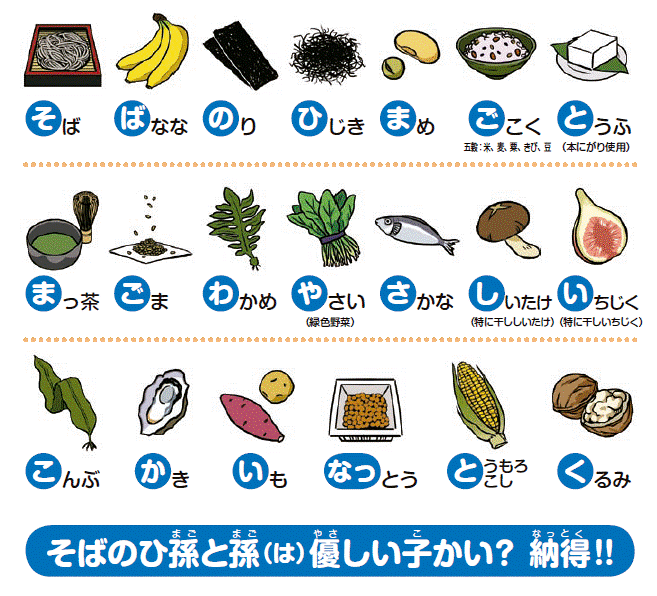
実際の食品でマグネシウムが豊富なものをいくつかご紹介します(100gあたりの含有量):
・海苔:1,300mg
・わかめ:1,100mg
・昆布:540mg
・ごま:360mg
・ごぼう:530mg
・大豆製品、ナッツ類、全粒穀物など
ただし、これらを毎日摂るのは簡単ではありません。食材の吸収率も考慮に入れながら、少量を毎日こまめに摂ることが大切です。
なぜ現代人はマグネシウムが不足しがちなのか?

本来、腎臓にはマグネシウムの再吸収能力が備わっており、簡単には不足しません。
しかし現代社会では、
・生理的・心理的ストレス
・精製糖や加工食品の過剰摂取
・炎症状態の慢性化
・飽和脂肪酸と果糖の高摂取
などにより、マグネシウムの吸収が阻害されたり、無駄に消費されたりしてしまいます。
まとめ

マグネシウムは糖代謝、神経系、ホルモン、筋肉の働きを支える非常に重要なミネラルです。
しかし現代の食生活やストレス環境では、不足や過剰な消耗が起こりやすいのが実情です。
ポイントは
・食事から少量ずつこまめに摂る
・不足を感じたらサプリメントを活用
・下痢などの副作用に注意しつつ自分に合った量を見つける
日々の食事に少し意識を向けるだけでも、体調の改善につながるかもしれません。
マグネシウムのすごさ、ぜひ今日から実感してみてください!
\\今の不調と体質を可視化//
 Metatron Oita
Metatron Oita